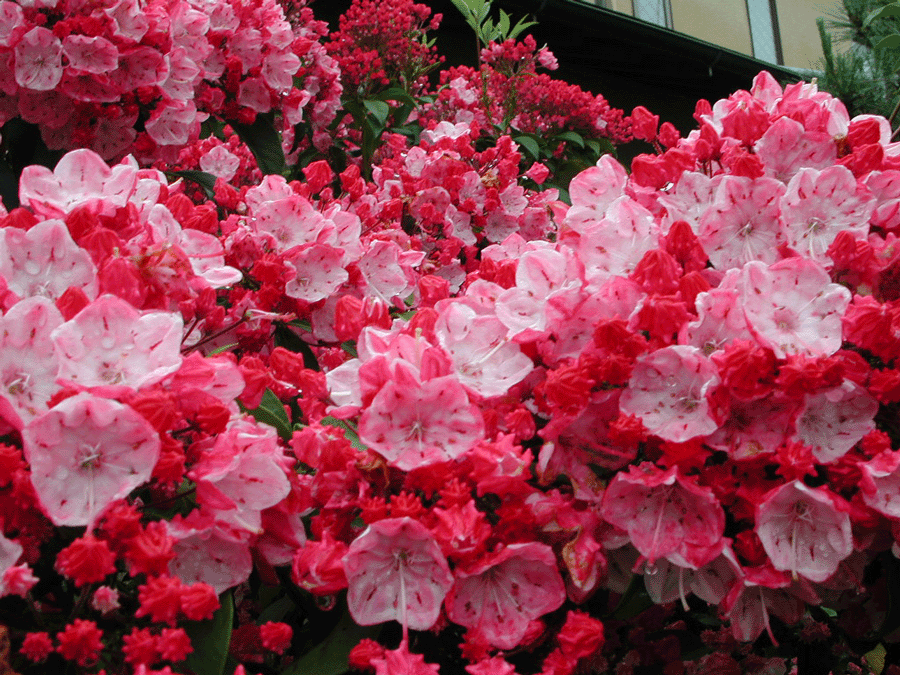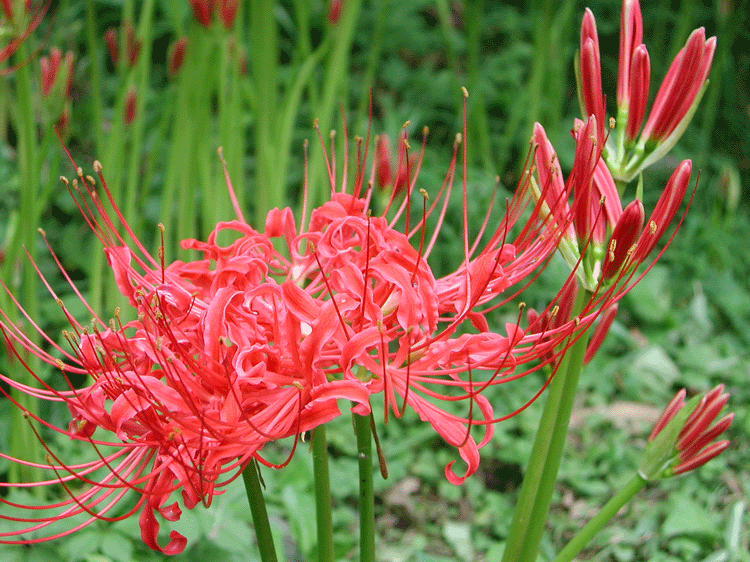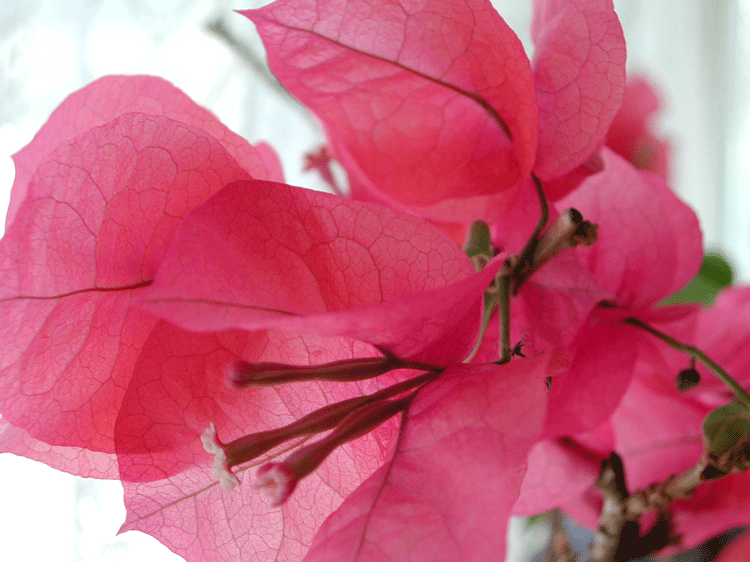
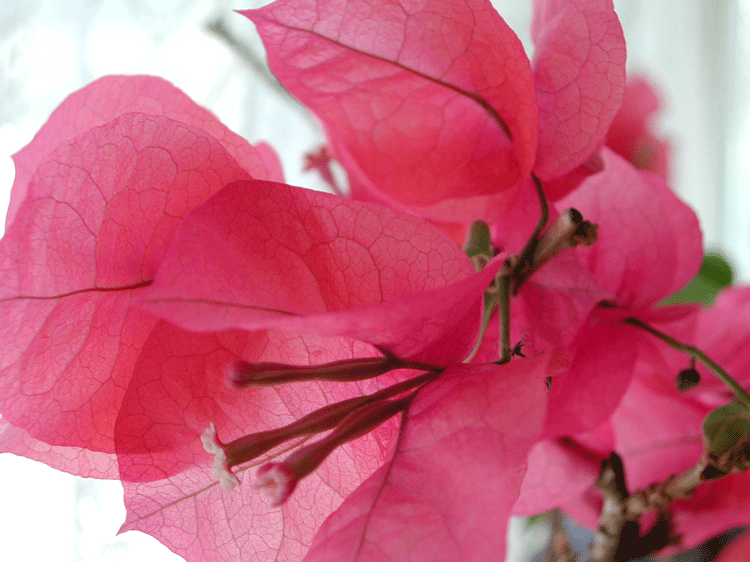
季節はずれのホトトギス
去年の秋に、庭の隅に生えているのを鉢に植え、室内においたホトトギス。小さなつぼみと花が咲いた。茎が長すぎたので途中で短くし、葉を見ようとしていたが、やっぱり自然のものは強い。室内の暖かさで時期はずれのこの時期にホトトギスが見られた。ホトトギスは花の斑点が鳥のホトトギスのようにみえるのでこの名づけられたらしい。変わった雄花と雌花はイカの足のようにもみえる。清楚で静かな雰囲気で心が穏やかになるこの紫の花が好きだ。

オンシジューム
中南米原産の着生ラン。買ってきてから3年目だが、今年も黄色い花を咲かせている。咲いている期間が長く丈夫な蘭だ。夏は木下に放置しておくだけで秋に室内に持ち込むと花が咲き出す。

鉢植えの山柿です。毎年葉の紅葉はすばらしいが、花は咲くけど実にならず、
親戚からもらってきた山柿、渋くてもいいからそろそろ実がならないとあきてくる。柿の実はドイツでもイタリアでもKAKIで売っている。最近ヨーロッパでも人気が出てきてどこのマーケットにもみられる。イタリアで栽培しているらしいが、なっているのは見たことはない。紅葉はきれいだが、鉢植えのせいか、あまり太らず盆栽にはまだまだ時間がかかりそう。
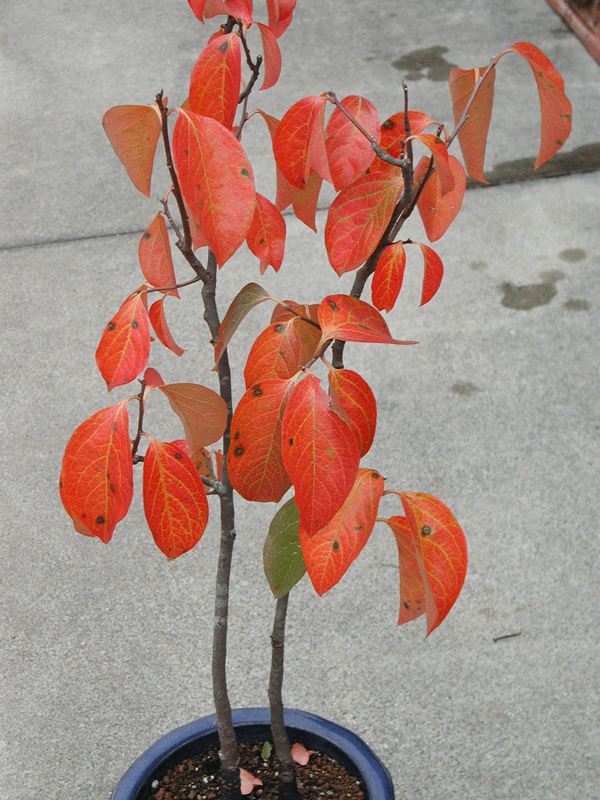
シャラ の紅葉
今年 山の紅葉を見に行けなかった人のために。我が家の姫シャラの紅葉です。毎年11月は真っ赤な葉になります。
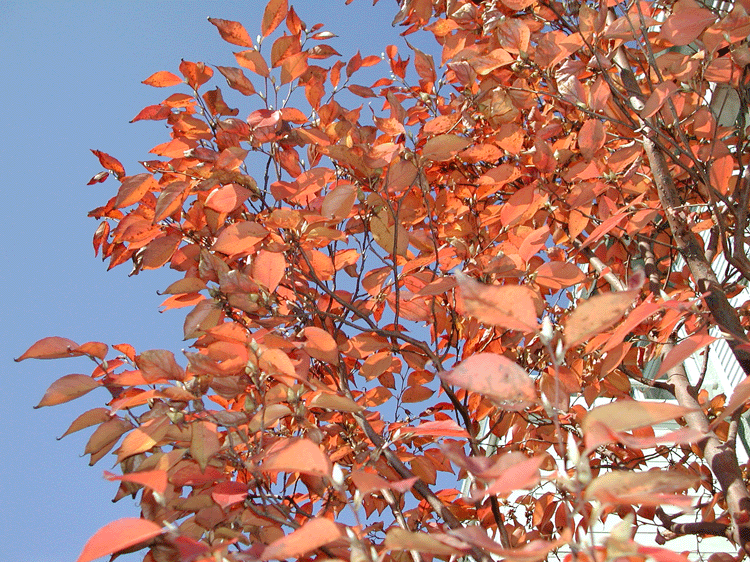
ツリフネソウ(釣舟草)
思川の上流付近 粟野町の思川沿いに咲く ツリフネソウが今年も咲いた。大きな、先端に巻貝のような渦巻きと水平に開いた二枚の大きな花弁、中は黄色い模様がある珍しい花が咲いている。花の蜜は奥深いところにあり、蜜を求めて集まった昆虫がこの筒に入り込むと中間に取り付けられた支えでぶらぶらと揺れる。この様子が船を吊り上げた様子に似ているのだろうと思う。花弁が開く前は貝のように見えるから不思議だ。
水車場は 釣舟草に 暮れかかる。 桂二
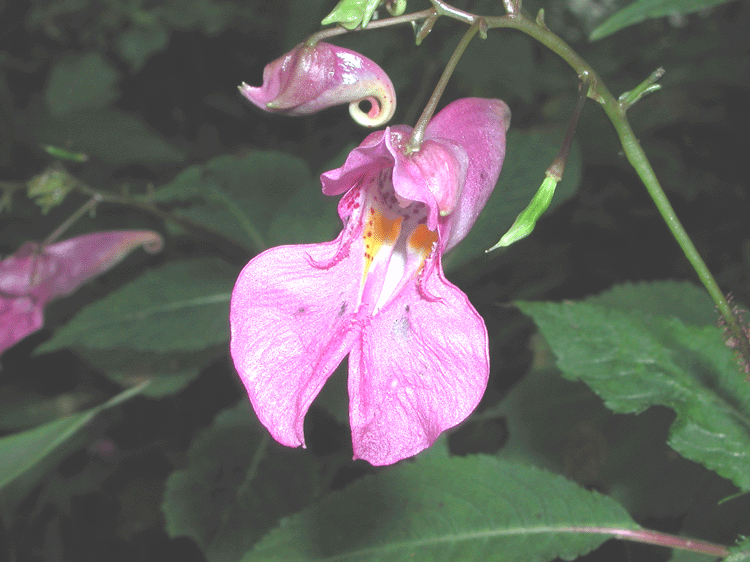
シュウカイドウ(秋海棠)
どこから来たのかシュウカイドウが庭の隅に咲き出した。つぼみのうちの真っ赤な色と、ピンクの花びらが印象的な草花である。鮮やかな黄色のオシベは実際にはあまり目立たない。園芸店ではベゴニアが売っているがこれと同じ種類だ。これの原種に近い。やや日陰の所を好むように時々道端に咲いているのが見られる。
秋海棠 西瓜の色に 咲きにけり 芭蕉
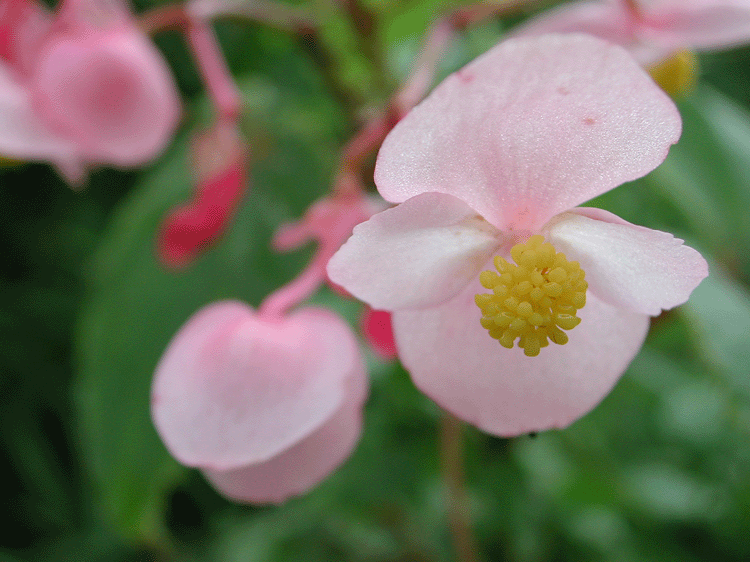
ヨイマチグサ(宵待草)
なんとなくロマンのある宵待草です。マツヨイグサ、月見草とも呼ばれる。一日で花が終わってしまうのでさびしいが白色のあでやかさは月見草の名にふさわしい。友人からもらった鉢植えがいつの間にか地植えになってしまった。その経過はわからないが毎年夏になると白い花を咲かせる。
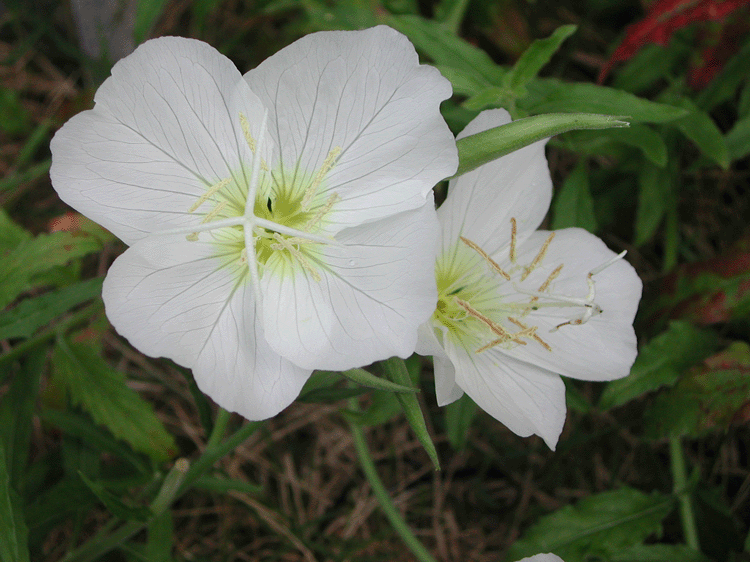
クマヤナギ(熊柳)
目立たない小さな花と赤い実が同時に楽しめる珍しい植物である。写真では赤い実の裏に見える、ぽつぽつとしたのが花。7月に咲いた花は翌年の夏に、2年かけて実が熟する。名前の由来は熊のように強いためといわれる。確かにこのつるは引っ張っても切れない。この写真は残念ながら家の盆栽ではなく近くの河原にあったもので、家にあるクマヤナギの盆栽はかなりの太さで花はさくが、実がなったことはない。今年は河原の花を取ってきて、受粉を期待しているが成果はまだわからない。
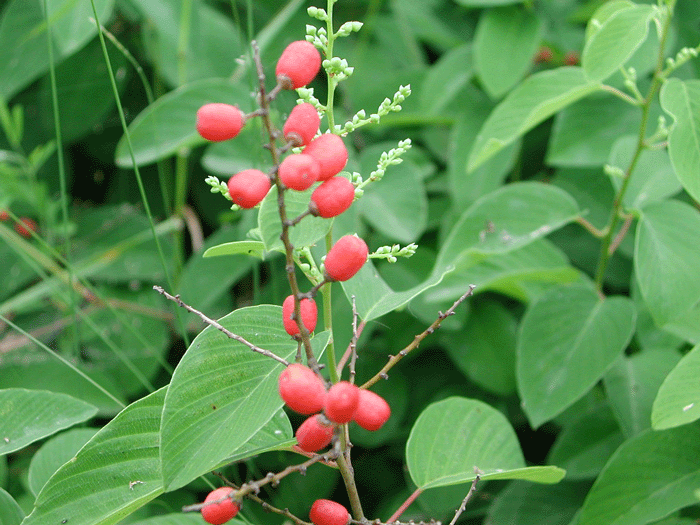
カルミヤ
今年はカルミヤが満開となりました。雨で花が重過ぎるくらいに垂れ下がった。真っ赤なつぼもが開くと薄いピンク色のなる。つぼみと開いた花が半々になるころが見ごろとなる。